『蒼球のフレニール』
アリル・ラルトのプライベートテイル8
どこまでも、どこまでも続く灰色の世界。
ゆめより怖い、ほんとうの迷宮。
迷い込むのも、出るのもあなた次第。
「ねぇねぇアリルちゃん、異世界のお宝って、どんなのかなぁ?」
異世界、灰色の空間を歩いていた一行の先頭に立つ、長い銀の髪の愛らしいヌーがそんなことをいった。少年のものとも少女のものともつかない済んだ声は、周囲に反響するでもなく灰色にすいこまれていく。
「そうだな、やっぱりきらきらぴかぴかなのはありきたりだしなっ。謎の石版なんかどうだ、ユゥリ?」
ヌー族の少年、ユゥリ・メルフィスがふらりと道筋からそれたりしないように方向を定ませつつ、金の髪の小さなちいさなヌーの少女アリル・ラルトがうなずく。
まるでピクニックにでも来ているかのようなのほほんとした空気に引率者、いや、保護者らしきイヌ族の女性、フレニール・ハンターのピエチェスカ・ルーインは思わず苦笑いをする。
『さまよう扉』の暴走がユグナリア王国に混乱をもたらして、もう長い。事態の核心に関わっているとはいえ、あっさりと順応してしまうのは冒険者としての性なのかもしれない。
さて、前を行く二人の妖精の冒険者としての素質はいかほどのものか。
考えかけて、やめた。いちおうF・Hの仲間とはいえ、アリルは種族の違いを越え実の妹のように思っている。たしかに将来は共に冒険したいという気持ちがないわけでもないのだが。ユゥリに至っては、アレだ。
苦笑いが本当の微笑みになる。ピエチェスカは、ストレートの金髪をさらりとかきあげた。
「いいよなぁ、おチビさんたちは気楽で」
ピエチェスカの仕草が合図になったかのように──実はそれまで彼女に見とれていた──声を発したイヌ族の男。
ピエチェスカはちらと振り返って男、アルマ・バグダスを見やる。
長身だ。流れの傭兵(確か武闘家と言っていた)らしく、体格もそれに見合う鍛え方をしている。グレイの毛並みに気のよさげな青い瞳、狼の精悍な顔つき。
「ま、そのぶん俺達大人がしっかりしなくちゃあな。どうだピエチェスカ、例のパートナーの話、考えてくれた……ぐは」
さりげなく肩に手をまわそうとしてきたアルマのみぞおちに無言で肘鉄をお見舞いし、ピエチェスカはため息をつく。すぐコレだ。
ふと、そういうことに関しては己を完全に律しているイヌ族の武人、F・Hの仲間の事を思い出す。あいつ最近見ないけど、どうしてるのかしら?
物思いは唐突に打ち破られた。
「あれは何だ!?」
緊迫……しているとは言いがたい嬉しそうなアリルの声が響きわたる。
しかしできたもの、アルマはするりと前に出て構えをとり、ピエチェスカもとっさに動けるように周囲に気を配る。
遠く前方に、白くぼんやりしたものが浮いていた。たまに不安定にふらり、ふらりと揺れている。
「なんだろうね〜」ユゥリのつぶやきの間にもどんどん近づいてくる。
「何だかわからないんだから、下がって!」
今にも飛び出していきそうなアリルを押さえ込みつつ、つい声を荒げてしまうピエチェスカ。
息を詰めて──口をふさがれているのもいるが──一同が見守る中、それは完全に姿を現わした。
赤い大玉に乗ったヌー。
「やぁ、こんにちは〜」
脱力する若干名をよそに、玉の上の華奢なヌーの青年はのんびりとあいさつをする。
まっ先に動いたのは、やはりといえばやはり、アリルだ。
誰も反応できない──その場の状況によるところも大きいが──瞬発力でまっしぐらに青年の元へと駆けていく。そのまま自分の身長よりも大きな玉にぴょんとはりついた。
誰もがひやりとしたが、玉乗りヌーは表情ひとつ動かすことなく驚異的なバランス制御力で自分と幼いヌーの少女を大玉の上に乗せている。
「あなたのこと見たことあるぞ!芸人さんなんだよな!」
「ニュウさんだったよねぇ?」
口々に問う同族の少年少女に彼、ニュウ・ブブリ・ドドンヴォリーはにこにことうなずく。単に目が細いから笑っているように見えるのかもしれないが。
真っ昼間に灯る白磁灯さながらのニュウの雰囲気に、真面目気質のイヌ族二人はただ立ち尽くすしかない。
「なあ、こんなトコで何してるんだ?私達と一緒に宝探ししないか?」
最近アリルはF・Hの後進の人材探しに余念がない。
「あ、ごめんー。オイラ今、ティヤオさがしてるんだ〜」
ティヤオって誰だ?アリルが考え込んだスキにユゥリが口を挟む。赤い大玉を指さした。
「いっつも、それに乗ってるねぇ?」
おそらく彼の玉乗り人生三十年間で幾度となく繰り返された問答であろうが、明るく答える。
「うん。だってこれに乗ってないと死んじゃうんだもんね〜」
死ぬ。一瞬固まるユゥリ。その間にすかさずアリルが問いを重ねる。
「ニュウの父さんや母さんも玉乗りなのか!?」
「ううん、オイラの父さんは空くじら乗りだもんね」
くじら。今度こそ、誰も聞いたことのない言葉だった。
「くじらはね。もともと海の生き物だもんね。お魚に似てるんだもんね〜」
ニュウは不可解な言葉をさらに発する。
「海?大陸の下にあるっていう、おっきな水たまりのコト?」
「ユゥリ、大陸の下にあるのはヴァン・ケトルだぞ。誰から聞いたんだ?」
しかしアリルの思考は完全に未知なるものへと向けられているようだ。目がキラキラと輝いている。
「そうか、空くじらか。オストランゼにも私の知らないものが一杯あるんだな!」
「オイラの生まれはエクセリアスの多島界だけど」
ニュウが訂正を入れる。が、アリルにはさして関係ない。行ってみたいところがひとつ、増えるだけのことだ。
「アリル……」
ピエチェスカがこめかみをもみほぐしながら、頭痛でもしているかのような顔つきで呼ばわる。
それから何かを察したらしいアルマが気を利かせ、まだ大玉の上にいたアリルを抱き上げた。
「あー、なにするんだ、アルマ!離せ!」
自分の四分の一の身長の少女に呼び捨てにされて、アルマの表情が変わる。
「俺のコトは『アルマお兄さん』と呼んでくれ!」
おじさん、と呼ばれるよりはマシかもしれない。
○
「じゃあね、今度会ったらオカリナ聴かせてあげるもんね」
ゴロゴロと去っていくヌーの青年を、アリルとユゥリは名残惜しそうに見送っていた。
その様子を見て、ピエチェスカはくすりと笑う。
「ほら、宝探しするんでしょ。行くわよ!」
「うん!」
「わ〜い」
なかよく歩き出す二人を見て、アルマがピエチェスカに言った。
「ま、こういうなごやかなのも嫌いじゃないね。それにほら、こうしてると俺達夫婦み…」
アルマは言い終えることができなかった。
「おじさん、こりないねぇ」
とどめはユゥリの無邪気な一言だったとかそうでないとか。
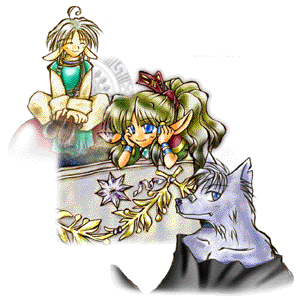
2000・11・あり