『蒼球のフレニール』
アリル・ラルトのプライベートテイル4
刻の翼ではばたくことはかなわない。
だって、わたしたちはみんな
鎖に繋がれているんだから。
「誰だ?」
声が聞こえたような気がして、アリルはあたりを見まわした。
ユグナリア王国首都から遠く離れたここアリランの、森の奥深い屋敷。古風だが美しく飾り付けられた廊下には、この小さな妖精しかいなかった。
ほかにはかすかな虫の声と、壁にそなえつけられた白磁灯の明かりだけ。
「ユゥリ……じゃないな」
夕食後のくつろぎをほうり出してまで捜している相手の名前をつぶやく。
アリルの幼なじみユゥリ・メルフィスは、「迷子になったんだ」と言えば「まあ、ユゥリ君が?」とすぐさま返ってくるほどよく迷子になる、銀の髪とすきとおった翠の瞳の妖精族だ。
「簡単に迷子になるかわりに、すぐに見つかるはずなんだけどな」
頭の上で結んである、彼とは対照的な暗い金髪をゆらしてアリルは目の前の扉を見上げる。各所に装飾をほどこされた重そうな扉だ。小さなアリルではそもそも取っ手に手が届かないが、この館のあるじであるユグナリア王女ラウリアの計らいで、館のすべての扉は開いている。
でも誰の声だろう?カトラの声だったような気がする。ユレシアかもしれない。
そっと扉に手をあてる。もしかしたら、このむこうにいるのだろうか?
○
クランベル公国ファーベランにあるグレイスン王女邸。
近衛兵のための一室には、一人の男性がいた。歳は二十代なかば。かなりの長身で、背中まである青みがかった黒髪をうしろで束ねている。
近衛らしく忠実そうな印象のととのった顔には、いまは思いつめたような表情が浮かんでいた。
いや、忠実というのは近衛という役職からくるものでは──レナ・プリンキピア王女に対してくるものでは──ないかもしれない。
と、男性がふと顔をあげて、扉のほうを見た。
「誰だ?」
同僚のものではない気配。誰何の声に応じるように扉が開き、小さな人影がころがり込んできた。
「子供?」
幼児かと思うくらい小柄だ。長い耳が見わけられた。ヌーの女の子だ。なぜ、こんなところに?
しかし油断はできない。子供を暗殺者として使う例もあるのだ。
先日の事件の記憶がよみがえってくる。彼はすっと身構えた。手がしぜんと剣にのびる。
そのあいだに少女は身をおこし、顔をあげてこちらをみた。
「なんだ……カトラじゃないのか」
「なんだって……」
初対面であからさまにがっかりされて、いきなり気勢をそがれる。カトラ?この屋敷にそのような名前の者はいただろうか。少女の耳にふと目をやった。うっすらと浮かんだクシーダ。
カサンドラ。
しかし、彼女は彼の標的ではない。
「ここがどこだかわかっているかい?」
わきあがる複雑な感情をおしとどめ、つとめて優しく語りかける。
「王女様の屋敷だろう?私はここにお泊まりしているんだ」
すぐに答えは帰ってきた。彼はかすかに安堵のため息をついた。自分は知らないが、王女の客か、あるいはその連れらしい。
「ここに男の子がこなかったか?ユゥリという名前なんだ」
妖精少女は彼の胸中に気付く様子もなく部屋をみまわしている。
「いや、ここには誰も来ていないよ」
「そうか、ありがとう」少女はいうなりきびすを返し、開いたままの扉の向こうへ姿を消した。
やや呆然とそれを見送っていた彼は気をとりなおして身体の向きを替え……扉を閉めようともう一度ふりかえると、さっきの少女がすぐ後ろに立っていた。こんどこそ彼は驚いた。
「ここはどこだ?あなたは誰だ!?」
いきなり問いつめてくる少女、アリルに、カノン・ルーベルフォングは正直に答えた。
「いや、そんなこといわれても……」
○
「そうか、カノンか。いい名前だな!」アリルはにこにこしている。
「あ、ああ」カノンは気もそぞろだ。
何せ……。
「あら、カノンさん、その子はどうしたんですかあ?」
「ルーベルフォングさん、迷子ですか」
人の多いこの屋敷では、廊下を行き交う者はひっきりなしだ。
小さなヌーの少女を肩ぐるまして歩く姿は目立つことこのうえない。
扉からきたのだから、扉から戻れるんじゃないかというアリルのいいかげんな推測を信じて、今屋敷中の扉を──可能なかぎり──開けて回っているところである。
怪しいことこのうえない。
ちなみに現在地は二階だ。
いま目立つわけにはいかないのに。カノンはあせりを感じていた。
「なにがダメなんだ?」
頭の上からひびく無邪気な大声にカノンはふだんの敏捷さを忘れてけつまづく。
「こ、心を読まないでほしいな」
おもわずあたりをはばかるカノン。
「口にだしてたぞ」
アリルが容赦なく指摘する。
「…………」
カノンはもうなにもいわず、黙々と作業をつづけた。
しかし、元気一杯の妖精少女はそれを許してくれない。
「カノンの目って、黒かとおもったらすこし緑なんだな」きれいだと笑う。
しかしこの状況はもはや肩ぐるまではないかもしれない。
そんなだから、カノンがすこしかがんだ拍子にアリルは彼の頭からころがりおちた。
あっというような一瞬だったが、半分は自主的におりたらしく、足からきれいに着地した。
「つぎはどの扉だ?私が開けるぞ」
だっと駆け出す。身長差でカノンはアリルを捕まえそこねた。止める間もなく手近な扉にとりつく。
「!!その部屋はダメだっ!」
アリルのあとを追ってその扉を音をたてていきおい良く開ききる。部屋の中の人物の視線がいっせいに彼に向いた。
そこにいたのは、メイドの女性がひとり、クライン・ドマーニュ製の自動人形に、そしていつもは寝室にひっこんでいるはずの部屋のあるじ。
「カノンさん……どうしたの?」
「ここに女の子が……」だんだん声がちいさくなる「……なんでもありません、失礼します」
作法にかなった礼をして、カノンはレナ王女の私室から退出した。
しばらく歩いて、人気のないところでぴたりと立ちどまり、疲れた表情で天をあおいだ。
「……なんだったんだ、いったい……?」
こたえるものはいない。
とびこんだ先は、見なれたアリランの屋敷の廊下だった。
「カノンはどうしたんだ?」
ふりむく。一瞬前までなにやら声がしていたようだが、もう聞こえない。扉を開けても、誰もいないだろう。
「それにあっちは外が明るかったな。ファーベラン……どこだろう。ピエ姐に訊けばわかるかな」
即断即決即実行。アリルは駆け出した。
再会をうたがわないこころ。
人に世に隔たりがあるとは思わないこころ。
じぶんの想いをしんじるこころ。
想いがそれを可能にする。
想いがみんな真実にする。
だから、それのどこが罪なのか。
わたしにはわからない。
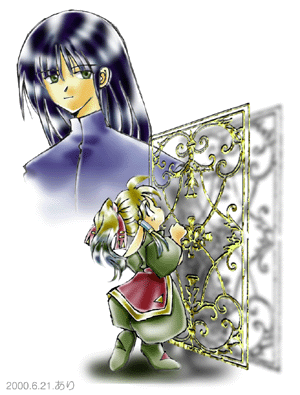
2000・6・あり