『蒼球のフレニール』
アリル・ラルトのプライベートテイル6
夏のはじめのある日。
その日は朝から雨がふり続いていた。
ときおり木々の合間をとおって吹いてくる風は、すこしの涼しさとあたたかなみどりのにおいをふくんでいる。
ユグナリア辺境都市、アリランにあるラウリア姫の館は、雨にいだかれて眠っているかのように静まりかえっていた。
「あんなコトがあったばかりじゃ、しかたないよね……」
開け放たれた窓のひとつに、ちいさな人影があった。窓わくにひじをついて頬杖をしている。
かすかな風にヌー特有の桃色の長い髪がさらさらと流れた。
成人して間もないだろう妖精族の、少女。ユーティス・ラズ・リューン。蒼穹をうつす水の色のひとみ。
そのまま何をするでもなく、ただ風にふかれていた。
いつもならこの館は滞在者たちの穏やかな、それでいて活気ある笑いにみちているはずだった。
事件は昨日、起こった。『夢見のオルゴール』の正体を知ってしまった者達がいたのだ。
オルゴールにふれたとたん、聞こえてきた声。それは拒絶。
ユーティスはそれだけだったが、『見て』しまった者もいた。精霊の贈り物をもつ者。
ぺた、とうしろで足音がした。ちいさなちいさな人影。
「ユーティス、か……?」
そこにいたのはおなじ妖精の少女、アリル・ラルトだった。
いままで寝ていたのだろう、いつもは頭の上で結われている髪はおろされ、服の装飾も外されていた。
「アリル、もう起きて大丈夫なの?」
かがみこむと、やっとユーティスの目線が下にくる。
「うん……ピエ姐は?」
ねぼけまなこでとことこやってきたアリルは左右をみまわす。
「ピエチェスカ?ボク、わからないや。ごめんね」
「そうか」
いつも明るくかがやいているはずの蒼い瞳が、暗くしずんでいる。ユーティスはなんだかたまらなくなった。どうやったら元気づけられるだろうか?
そういえば、あれがある。
「そうだ、コレ、とっておきのやつ。一緒に食べようよ」
ユーティスは肩からさげていたカバンをさぐると、いつものキャンディーのかわりに柑子をとりだした。
「わあ」
「へへー。昨日オストランゼからついたばっかりなんだって」
手つきがおぼつかないアリルに皮をむいたのをはんぶんこしてやる。
ひとくち食べたアリルは顔をしかめた。
「すっぱい」
「あはは。ボクこれ好きなんだ」
ぱくりとおいしそうに柑子を口にほうりこんで笑うユーティス。
もらった食べものはきちんと食べるようにいわれているらしく、アリルは顔をしかめたままいっしょうけんめい食べている。
「そういえばオストランゼはもう冬なんだよね」
そんなアリルの様子をながめながら、庭先になっていた柑子の樹を思い出すかのようにユーティスがいう。
「そういえば、アリルはさみしくないの?お父さんやお母さんはオストランゼにいるんだよね?」
「うーん……ユゥリもいるし、大丈夫だ」
なんともなさそうなアリルに、ユーティスは首をかしげる。アリルははっとしたように、あわてて言いたした。
「私の父さんと母さんは紋章技師の修行のためにグレイスンに行ってたことがあるんだ」
「ああ、そうか。そうだよね」
ユーティスは得心がいったというようにうなずいた。
「ボクもアースラントに行ってお勉強したんだよ。オルゴールの」
「へえ……ユーティスは自分で曲をつくるのか?」
興味津々といった年下の少女にはにかむように答える。
「ううん、それはまだだよ。でもいつかはね」
そしてまたカバンのなかをさぐりだした。
布につつまれていたそれを取り出すと、ちいさなしろい木箱だった。その表面はきれいにみがかれて、素朴ながらもていねいに飾りもようが彫られている。
「これ、師匠にもないしょでつくった、ボクのはじめての作品なんだ」
ふたをあけると、ひとりでにメロディを奏でだす。アーキテクトのオルゴールにネジは必要ないのだ。
どこか懐かしい、しかし楽しげな響き。天空にきらめきおどる星々と精霊に捧げる唄。
「これ、星まつりのうたいか?」
聞き知った曲におどろいたように声をあげるアリル。
「アリルの村でもおんなじ曲だったんだ!」
「ユーティスの村でもおなじ祭りをやってたんだな!」
おたがいうれしそうに表情をかがやかせる。
箱をふたりの間において、聖なる炎とする。
そらに散る、はじまりの巨人ミルグの涙をあおぐように唄い踊るのだ。
歌い継がれる、忘れられたことば。記憶の彼方の音楽。
ほんとうの祭りのときには、ヌーもドロンドロンも動物たちですら村に住むものすべてが炎を囲んで踊る。
ここには妖精がたったふたりだけ。
それでも歌い、踊る。
世界への祈り。想いはおなじ。
「アーティサンて素敵だなっ!」
くるくるまわりながらアリルが言った。
「そうかな、ボクはおくりものをもらってるキミたちの方がすごいとおもうけど」
「ユーティスもその気になればおくりものはもらえるぞ?もらってみるか?」
「うーん……」
ユーティスのこまった顔をアリルが笑う。もう、だいじょうぶだ。
ふたりの妖精はつかれてへとへとになるまでずっとずっと踊り続けていた。
雨はまだふり続いていたけれど、雨はやさしいし、それにいつかきっとやむのだ。
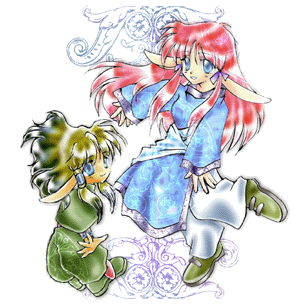
2000・7・あり